 |
|
| 1.要約 |
 |
| 本試験では、未熟なふん尿が、扱いやすくかつ安全な腐熟堆肥に至るまでの処理日数を求めるため、処理日数と腐熟化程度との関係招調査した。試験は、十勝管内更別村の堆肥舎で平成10年4月28日から開始した。堆肥原料は牛ふんと麦稈とし、原料重量は8tとした。また、堆肥原料の堆積条件を水分70%、堆積高1.8mとした。切返しはマニュアル1)に従い、月1回程度行った。 |
| 試験の結果をまとめると、以下のようになる。 |
| [1] |
堆肥温度は、堆積直後および切り返し後70℃まで上昇し、順調に発酵が進んだ。 |
| [2] |
C/N比は、処理14日目に16まで急激に低下、60日目には14となりその後はほとんど変化がなかった。 |
| [3] |
コマツナ発芽率は処理60日で90%以上に達し、生育障害も認められなかった。 |
| [4] |
臭気指数は、処理30日目に急減し、その後はほとんど変化がなかった。 |
| [5] |
臭気強度は、処理30日目で「不快感を持たない濃度」まで低下した。 |
|
| 以上のように、適正な条件で処理された牛ふんは、処理開始後60日目で作物に対し安全で、扱いやすい腐熟堆肥となることが明らかとなった。しかし、堆肥の腐熟は管理方法で変化することから、本書では安全性を考慮し、腐熟堆肥に至る処理日数を90日とした。 |
| 2.試験結果 |
 |
| 堆肥温度は原料堆積直後に70℃まで上昇した。その後、徐々に低下したが、切り返し毎に70℃に達した。このように高温になることは微生物が盛んに活動していることであり、腐熟化が順調に進行したことを示している。高温によって、病原菌や寄生虫、雑草の種子を死滅させる効果が得られる2)。 |
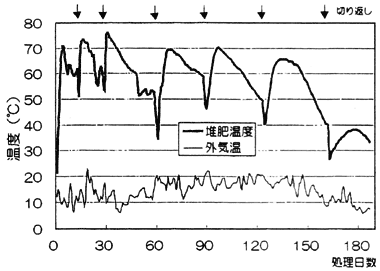 |
| 図1 麦稈堆肥の温度推移 |
| C/N比は、堆肥の腐熟度を示す指標の一つと考えられている。副資材として麦稈を用いた場合、その目標値は20以下が望ましい3)。本試験では、堆積直後のC/N比は27であったが、14日目に16まで急激に低下した。その後処理60日には14となり、それ以降はほとんど変化がみられなかった。 |
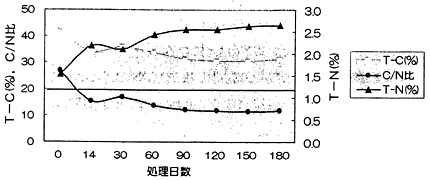 |
| 図2 処理日数の経過に伴うC/N比の変化 |
堆肥の腐熟化の進行に伴い、ふん尿中あるいは副資材中に含まれる生育阻害物質は減少する3)。これらの物質の残存程度、作物の生育阻害程度を調べるために、コマツナを用いて発芽試験を行った。
その結果、発芽率は未処理(0日)では60%と低かったが、処理日数の経過に伴って高くなり、60日目には90%以上に達した。また、60日目以降の堆肥にはコマツナの生育障害は認められなかった。 |
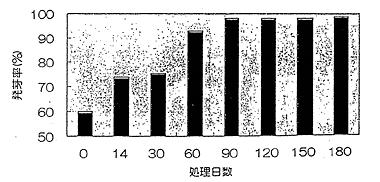 |
| 図3 コマツナの発芽率 |
堆肥の臭気指数は処理14日目で43と高くなったが、30日目には17まで低下し、それ以後180日までほとんど変化がなかった。
また、表1に示したように、規制の対象となっているイオウ系化合物、低級脂肪酸等の悪臭物質はいずれも処理30日目で「不快感を持たない濃度」(臭気強度2.5,参考資料I参照)までに低下していた。 |
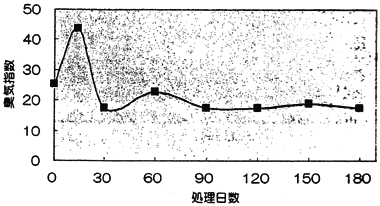 |
| 図4 臭気指数の推移 |
| 表1 悪臭戦分の臭気強度の変化 |
 |
| 処理日数 |
分析値(臭気強度) |
| 0日 |
14日 |
30日 |
60日 |
90日 |
120日 |
イオウ系
(μg/㎏) |
硫化水素 |
180(3.0) |
47(2.5) |
2.6(0.0) |
0.9(0.0) |
0.7(0.0) |
0.3(0.0) |
メチル
メルカプタン |
100(4.0) |
7.7(2.5) |
1.1(1.0) |
2.7(2.0) |
<0.5(0.0) |
<0.5(0.0) |
| 硫化メチル |
46(2.0) |
9.3(2.0) |
2.8(1.0) |
1.8(1.0) |
<0.5(0.0) |
<0.5(0.0) |
| 二硫化メチル |
<0.5(0.0) |
<0.5(0.0) |
<0.5(0.0) |
<0.5(0.0) |
<0.5(0.0) |
<0.5(0.0) |
低級
脂肪酸
(㎎/㎏) |
プロピオン酸 |
130(2.5) |
1.0(0.0) |
1.4(0.0) |
0.9(0.0) |
17(1.0) |
-(-) |
| イソ酪酸 |
24(-) |
1.4(-) |
1.5(-) |
0.6(-) |
0(-) |
-(-) |
| ノルタル酪酸 |
220(4.0) |
1.6(1.0) |
1.9(2.0) |
1.5(1.0) |
0.5(1.0) |
-(-) |
| イソ吉草酸 |
48(3.5) |
5.5(2.5) |
6.5(2.5) |
3.6(2.0) |
0.2(1.0) |
-(-) |
| ノルマル吉草酸 |
35(4.0) |
2.9(2.0) |
4.1(2.5) |
1.9(1.0) |
0.1(0.0) |
-(-) |
| 6段階臭気強度 |
4.0 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
1.0 |
- |
|
| 堆肥の水分は、処理日数の経過に伴い減少し、処理60日目で57%まで低下した。一般に、水分率が低いほど運搬、圃場散布の面で扱い易くなる。家畜ふん堆肥の品質基準4)によると、水分率は70%以下が望ましいとされている。 |
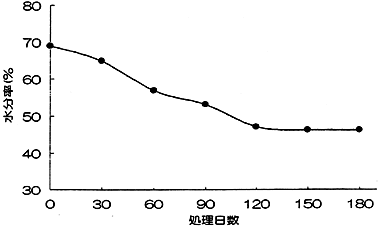 |
| 図5 処理日数の経過に伴う水分率の変化 |
| 2.まとめ |
 |
| 本試験の結果、牛ふんを麦稈で水分調整し適正に腐熟化処理を行った場合、60日で作物に対し安全、かつ扱いやすい腐熟堆肥になることが明らかになった。しかし、堆肥の腐熟は管理方法により左右されやすいことから、本書では、腐熟堆肥に至る処理日数を90日とした。 |
本書ではハウス乾燥施設をふん尿の水分調整施設として位置づけ、ふん尿処理基本システムに取り入れている。
ハウス乾燥施設は、含水率の高いふん尿を薄く広げ、太陽エネルギーと風を利用して乾燥を促すものである。この施設は温暖地で従来から利用されてきたもので、建設費やランニングコストが安く、維持管理が容易で、労力がかからない等の利点がある。しかし、寒冷地での実績は少なく、処理能力など不明な点が多い。
このため、本試験では既存施設を利用して積雪寒冷地におけるハウス乾燥施設の処理能力を明らかにした。 |
| 1.要約 |
 |
| 試験は、十勝管内中札内村の酪農施設で平成9年11月から平成10年10月までの期間で行った。原料は堆肥盤に堆積された水分80%程度の生ふん尿を用い、これに乾燥ふん尿を混合し乾燥処理を開始した。乾燥目標水分をおおむね60%以下として調査を行った結果、次の点が明らかとなった。 |
| [1] |
3~10月の水分蒸発量は、3.7~5.8㎏/m2・日の範囲にあり、この期間の平均は4.8㎏であった。 |
| [2] |
11~2月決低温で乾燥能力が極端に低下することから、水分蒸発量がほとんどなく、乾燥を見込むことができなかった。 |
| [3] |
処理中のふん尿の温度は最高で52℃に達したが、日数の経過とともに低下し、高温状態を長く維持することができなかった。 |
| [4] |
コマツナ発芽率は、乾燥処理が進むと時期により90%と高くなるものの、生育障害は解消されなかった。 |
|
| 以上のことから、十勝におけるハウス乾燥施設の水分蒸発量は、春~秋期で平均4.8㎏/m2・日であり、昨年公表した「家畜ふん尿検討資料」で採用した3.0㎏よりも多いことが明らかとなった。水分蒸発量は年変動があることから、本書では施設規模の算定に用いる値を4.5㎏/m2・日とした。ただし、冬期は乾燥能力がほとんど見込めない。また、本施設だけの腐熟化は不可能であるため、乾燥後の腐熟化処理が必要である。 |
| 2.施設の概要 |
 |
| 表1 ハウス乾燥施設の概要 |
 |
| 構造・機械 |
材質・規格 |
| ハウス |
骨材 |
鋼性パイプ |
| 屋根材 |
強化ビニール |
| 長さ |
55.5m |
| 間口 |
15m |
| 面積 |
837m2 |
| 発酵槽 |
幅 |
6.0m |
| 高さ |
0.3m |
| 長さ |
53.7m |
| 撹拌・移送機 |
形式 |
岡田式畜ふん乾燥装置D-300-6型 |
| 幅 |
6.7m |
| 高さ |
0.9m |
| 搬送距離 |
約50㎝/回 |
| 速度 |
2.8m/分 |
| 機械総重量 |
1,050㎏ |
| 運転操作 |
完全自動式 |
|
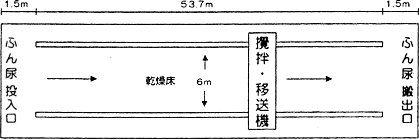 |
| 図1 ハウス乾燥施設内の平面配置図 |
 |
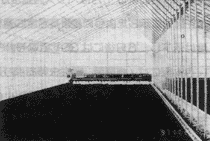 |
| 写真1 ハウス乾燥施設の外観 |
写真2 施設の内部と撹拌移送機 |
| 3.調査結果 |
 |
| [1] |
3~10月の水分蒸発量
ふん尿の処理量と乾燥処理前後の水分率から、月別の水分蒸発量を求め表2に示した。水分蒸発量は3月では3.7㎏/m2・日と少ないが、夏期の6月~8月には5㎏以上と多くなり、季節により大きく変動した。
一般的に、ハウス乾燥施設の水分蒸発量は、関東以南の地域で4.5~5.0㎏(夏期)とされており、この数値を基に施設設計されている1)。本試験の結果では、冬期以外の期間(3~10月)の平均は4.8㎏であることから、十勝のような寒冷地においても温暖地と同等の能力を見込むことができる。 |
|
| 表2 ハウス乾燥施設の処理能力 |
 |
| 月 |
水分蒸発量
(㎏/m2日) |
| 3 |
3.7 |
| 4 |
4.0 |
| 5 |
4.5 |
| 6 |
5.8 |
| 7 |
5.5 |
| 8 |
5.4 |
| 9 |
4.8 |
| 10 |
4.7 |
| 11 |
0.0 |
| 12 |
0.0 |
| 1 |
0.0 |
| 2 |
0.0 |
| 平均 |
3~10
月 |
4.8 |
| 年間 |
3.2 |
|
 |
| 注)3月および4月は、水分蒸発計の測定値から推定した |
| [2] |
11~2月の水分蒸発量
表2に示したように、冬期間(11~2月)の水分蒸発量は全くなく、乾燥を見込むことができなかった。これは、外気温な日射量の低下によるところが大きい。
|
|
ふん尿の温度は、混合した原料を施設に投入した後5~10日で最高温度に達した。特に、6月および7月はハウス内温度が上昇したことから、50℃以上を示した。しかし、図2に示したように、最高温度に達した後、乾燥処理日数が経過するに伴って温度は低下し、6日後には30℃となり、その後は25℃程度わで緩やかに下がった。
ふん尿には、病原菌、寄生虫卵および雑草種子が含まれることがあり、これらが死滅するためには堆肥化の過程で60℃以上の高温が必要とされている2)。したがって、本施設のみでの腐熟化は不可能であり、あくまで乾燥施設として利用するのが適当である。 |
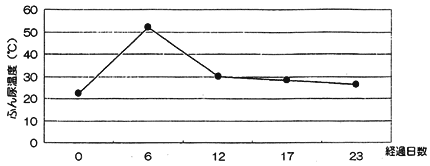 |
| 図2 乾燥過程におけるふん尿温度の推移 |
| コマツナの発芽率は、試料の採取場所や時期によるバラツキが大きかった(表3)。7月および8月の乾燥処理後の試料は発芽率約90%を示したが、これらの試料ではコマツナの根に伸長抑制や褐変症状が認められた。したがって、本施設で処理したふん尿には、作物の生育阻害物質が分解されず残っていることが換測される。 |
| 表3 乾燥処理されたふん尿のコマツナ発芽率 |
 |
| 試料 |
採取場所 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
| 原料 |
堆肥盤 |
1 |
- |
- |
92 |
37 |
| 乾燥処理前 |
乾燥施設ふん尿投入口 |
7 |
39 |
40 |
45 |
80 |
| 乾燥処理途中 |
乾燥施設中央 |
- |
- |
83 |
66 |
51 |
| 乾燥処理後 |
乾燥施設ふん尿搬出口 |
49 |
72 |
90 |
89 |
67 |
|
| 4.まとめ |
 |
ハウス乾燥施設の能力試験の結果、3~10月の水分蒸発量は平均4.8㎏/m2・日の値が得られたが、施設規模の算出には4.5㎏の値を採用する。
また、十勝の冬期においては、本施設の水分蒸発能力は期待できないことがわかった。 |
|
 |