 |
|
本編では、糞尿処理施設の低コスト化を主眼に置き、処理方法を再検討するとともに、糞尿回収量の見直し、現場レベルでの堆肥化試験による腐熟期間の見直しやハウス乾燥施設の乾燥能力の見直し、低コスト建築物の採用等を積極的に行うものとした。
施設の低コストに向けての主な取り組みを以下にまとめた。 |
| 表3-1 施設の低コスト化への取り組み |
 |
| 低コスト化への取り組み |
本書における考え方 |
従来の考え方 |
| [1] |
ふん尿回収量の見直し |
糞:30kg
尿:20kg(含む汚水) |
糞:40㎏
尿:20kg |
| [2] |
堆肥の腐熟期間の見直し |
90日間 |
165日間 |
| [3] |
ハウス乾燥施設の
乾燥能力の見直し |
4.5kg/m2・日
(除く冬期間) |
3.0kg/m2・日
(除く冬期間) |
| [4] |
低コスト堆肥舎の採用 |
木造、PT型ハウス
堆肥盤と上屋を分離
堆肥盤と側壁高は1.2m |
鉄骨構造
堆肥盤と堆肥舎は一体
堆肥盤と側壁高は2.0m |
| [5] |
低コスト乾燥施設の採用 |
鉄骨造、D型ハウス
処理槽側壁はコンクリート2次製品 |
アルミパイプ構造
処理槽側壁は現場打ちコンクリート |
| [6] |
堆肥舎の貯蔵部分を廃止 |
堆肥貯蔵施設の廃止 |
堆肥舎に6カ月の貯蔵部分を確保 |
| [7] |
尿処理のばっ気槽と貯溜槽の一元化 |
ばっ気槽を廃止し貯溜槽でばっ気を行う |
ばっ気槽と貯溜槽を設置 |
|
最近の高必乳化により、乳牛から排せつされる糞は40㎏、尿は20㎏とするのが一般的である。従来はこれらの糞と尿を全量回収するものとして施設規模を算定していた。
本編では、 |
| 基本システムは、牛舎から排出される糞尿の性状別に、その性状に適した処理方法をまとめたものである。 |
| [1] |
放牧やパドックで排せつされる糞と尿は回収することが不可能である。 |
| [2] |
冬期間の舎飼期において1日6時間程度はパドックでの飼養となる。
との考えから次のような計算で算出した処理量を採用した。 |
| |
糞 : 40×(24-6)÷24=30㎏/頭・日
尿 : 20×(24-6)÷24+※=20㎏/頭・日 |
| |
*は汚水部分として処理量にカウントする。 |
現場レベルで堆肥の腐熟化試験を行った結果、所定の水分調整(70%)を行った糞尿は、適時切り返すことで60日間で十分な腐熟堆肥になることが確認された。
本書では堆肥化に必要な腐熟期間を、安全性を考慮して90日間として計算する。
なお、試験の詳細は巻末の「堆肥の腐熟化試験」に示す。 |
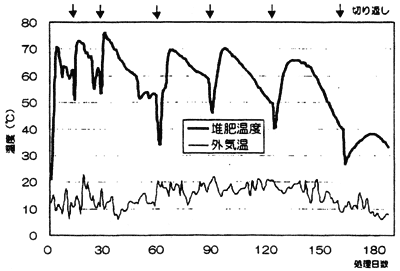 |
| 図3-1 腐熟化試験における温度推移 |
既存のハウス乾燥施設を利用して、年間を通した乾燥能力の試験を行った結果、冬期間以外の乾燥能力は寒冷地においても4.8kg/m2・日であった。
この結果から、本書では安全率を見込んで4.5kg/m2・日で計算している。
なお、試験の詳細は巻末の「ハウス乾燥施設の能力試験」に示す。 |
堆肥舎は、農林水産業用PT型ハウスを採用することにより、建設コストの縮減を図る。
構造は木造であり1棟の最大面積を500㎡以下とすることで、建築基準法適用外の建築物として取り扱うことができる。
また堆肥盤とは分離した構造とし、施設整備における自由度の向上を図ることができる。側壁を設ける場合は壁高は1.2mとした。 |
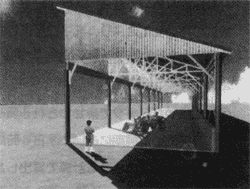 |
| 図3-2 PT型ハウスを利用した堆肥舎 |
ハウス乾燥施設は、乾燥能力の低下する冬期間(11月~2月)は稼動を休止し屋根等の被覆材を取り外す構造とすることにより、仮設建築物として取り扱う。
また、構造は屋根部をアーチ構造とする鉄骨造・D型ハウスを採用し施設の低コスト化を図る。
さらに、乾燥処理槽側壁をコンクリート2次製品とすることでさらに低コスト化をはかれる。 |
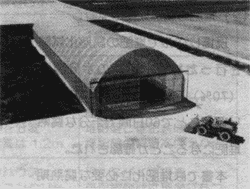 |
| 図3-3 D型ハウスを利用したハウス乾燥施設 |
| 腐熟化した堆肥は、環境に負荷を与える恐れがないことから、堆積場に搬出しシート等で覆う。 |
| スタンチョン牛舎から排出される尿は、貯留槽に曝気装置を設置し、ここで曝気処理を行うことで低コストを図る。 |
|
 |