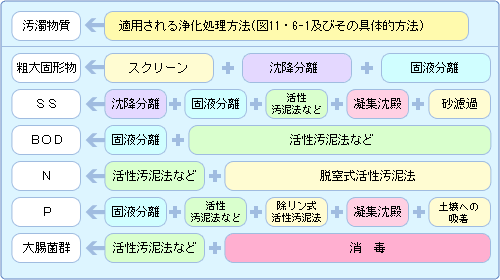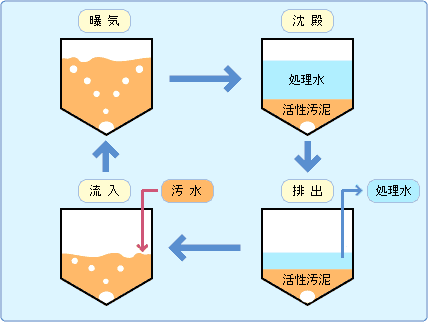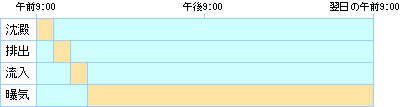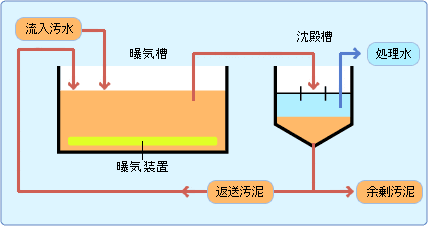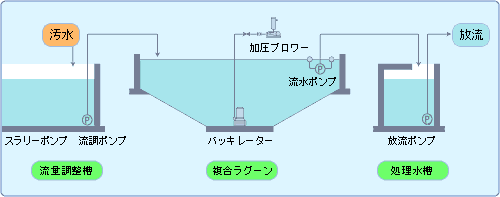| (6)汚水処理について 畜舎から発生する尿を中心とした汚水や固液分離した液分の処理方法には、浄化処理をして経営外へ放流する方法、曝気処理などにより臭気の発生を抑えるとともに、牧草や作物に障害が起きないように処理をしてから、圃場に散布する方法などがあります。 1)浄化処理について 家畜ふん尿はできるだけ有機物資源として有効利用することが理想ですが、すべてを有効利用することは困難です。そのため、環境汚染を発生させないように適切な浄化処理をした後で経営外に放流する必要があります。
家畜ふん尿の浄化に用いられる主な処理方法は、大きく物理的処理、化学的処理、生物学的処理の3つに分けられますが、固液分離(物理的処理)したあと、活性汚泥法(生物学的処理)で浄化し、処理水を消毒(化学的処理)するというように多くの場合これらの処理方法が組み合わされて処理されています。
それでは、浄化処理方法の中で最も一般的な活性汚泥法について紹介します。 活性汚泥法は、浄化処理効果が高く、人間の下水処理にも使われている生物学的処理方法です。ただ、維持管理が難しく、電気量などの経費が多くかかることが欠点です。畜産業の中では養豚農家を中心に導入されています。現在、酪農家に導入されるケースは少ないのですが、今後、尿などの液状物を施用する農地がない場合には活性汚泥処理法の導入が必要となるでしょう。 活性汚泥とは汚水を浄化する「活性(能力)」を持った「汚泥(微生物の付着した固まり)」を使う方法です。活性汚泥が汚水中の汚濁物質(有機物など)を消化(分解)し、新しい活性汚泥を生成しますが、その時に汚泥を沈殿分離させると上澄液として浄化された水が得られます。この処理方法では、曝気により汚水に溶存した酸素を微生物が有機物とともに消費して二酸化炭素を放出しながら増殖しますが、活性汚泥の量は次第に増加するため、ときどき余分な汚泥を引き抜いて活性を一定に保つ必要があります。 この活性汚泥法は大きく回分式活性汚泥法、連続式活性汚泥法、曝気式ラグーン法の3つに分けることが出来ます。 回分式活性汚泥法はひとつの曝気槽で流入、曝気、沈殿、放流の4工程を1日単位で繰り返す方法です。処理施設は沈殿槽や定量投入装置、汚泥返送装置などが必要ないのでシステムは単純で、建設費も安くなります。また、維持管理も比較的容易なため中小規模の経営に向いていますが、施設規模はやや大きくなります。
連続式活性汚泥法は曝気槽に沈殿槽を併設し、汚水を連続的に処理できる施設で、下水処理場のほとんどは連続式の活性汚泥法です。連続式活性汚泥法にはいくつかの方法があり、それぞれに適用規模、処理能力、設置面積、維持管理技術、経費、施設費等が異なり、家畜尿汚水の浄化処理には、主に標準活性汚泥法、長時間曝気法、酸化池法(オキシデーションデッチ法)が利用されています。
曝気式ラグーン法は回分式活性汚泥法をさらに大きくした形態で、曝気槽の容量が大きく、汚水の滞留時間が長いため、負荷の変動に強く、余剰汚泥の発生量も少ないため、管理は容易ですが、広い敷地が必要となります。
2)曝気による液肥化処理について 浄化処理は処理液を経営外に放流することを前提としているため、水質汚濁防止法の排水基準に合わせた処理をしなければなりません。曝気処理では処理液を圃場散布できるようにするため、散布時には臭気が発生しないように、また、牧草などに障害が起きない程度にまで曝気します。 以上、汚水処理について簡単に紹介しました。先に家畜ふん尿はできるだけ資源として利用すべきと言いましたが、畜舎汚水の利用は困難な点が多く、また、高度な専門知識・技術を要する分野であるため非常に厄介なものです。しかし、環境汚染を引き起こさないためには避けて通ることが出来ない問題です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |