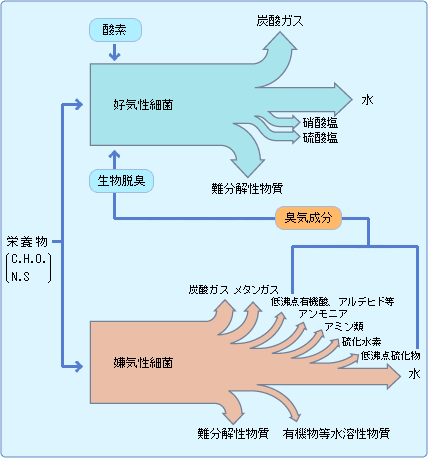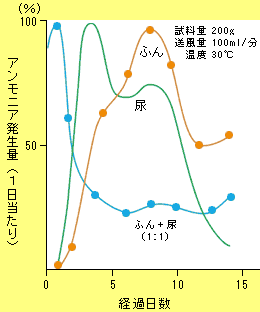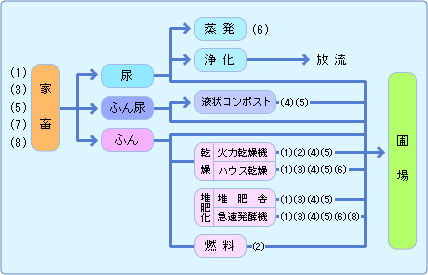| 世間の環境問題に対する意識への高まりと、市街化の急速な進展の中、悪臭問題は畜産にかかわる苦情の中で最も大きなウェイトを占めています 畜産生産者の皆さんや畜産関係者である私たちは「畜産には臭いがつきものだ」と、考えるのですが、一般社会ではそのように考えていただけないのが現実です。現に悪臭防止法なる法律も制定されており、「畜産には臭いがつきもの」とは言ってられない状況になっています。 それでは、畜産につきものの臭気対策はどのようにすれば良いのでしょうか。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)敵(臭気)の正体 畜舎内から発生する臭気は、主としてふん尿や飼料そして家畜の体臭です。その中でも、皆さんご存じの通り、ふん尿から発生する臭気が一番大きな問題です。確かに、粗悪なサイレージやふん尿まみれになった家畜が臭気が発生源となる場合もありますが、ふん尿から発生する臭気を抑えることが最も良い解決になります。 ふん尿由来の臭気成分は、質的には畜種による違いはほとんどなく、何十何百という臭気成分の量的なバランスの違いで各畜種毎に特有の臭気を作り上げています。 |
||
| (2)臭気の発生について 皆さんは経験的に新鮮なふん尿は、さほど臭くないと思いませんか。確かに臭いことには違い有りませんが・・・・。 新鮮なふん尿から発生する臭気は時間の経過とともに変化します。これは細菌が、時間の経過とともにふん尿中の有機物を分解することが原因で、また、発生する成分は好気的(酸素が一杯)条件と嫌気的(酸素がない)条件によって異なります。 好気的条件を好む細菌は有機物を分解すると主に炭酸ガス(無臭)と水を作りますが、嫌気的条件を好む細菌はアンモニア、硫化水素などの臭気成分を多く作り出します。
次に管理方法の違いによる発生臭気の差についてですが、これはふんと尿が混合している場合(ふん+尿)に比べ、ふんと尿を分離してやると臭気の発生が遅くなることも示しています。また、ふん及び尿は新鮮な時にはアンモニアの発生が少ないのですが、時間が経過するとアンモニアが多く発生することを示しています。これらのことはアンモニアだけでなく、その他の臭気成分にもいえます。
さらに、毎日除ふんと水洗をして畜舎を綺麗にしていれば、清掃しない場合に比べ発生する臭気の種類が少なくなります。
以上のことから言えることは、1)畜舎を綺麗にする。2)ふん尿を嫌気的にしない。3)ふんと尿は速やかに分離する。3)速やかにふん尿の処理を行なう。以上3点が畜舎から悪臭を発生させないためのキーワードです。 |
||||||||||||||||
| (3)設備・装置による脱臭方法 畜舎については、先に3点が十分に達成できるならば、大きな問題は発生しないと考えられますが、労力や施設の構造上無理がある場合やふん尿処理施設から高濃度の臭気が発生している場合には、設備・装置による脱臭方法を検討する必要性があります。 脱臭方法には様々な方法がありますが、発生させてしまった臭気を脱臭するには多額の設備投資とランニングコストを要するものが多く、また、低コストを謳い文句にしているものは、持続効果や能力に問題があるケースが多いようです。ただ、どの方法にしても完璧な(能力、コストetc.を満たす。)ものはないのが現状です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)脱臭資材について これまで述べてきたように、悪臭対策は畜舎清掃作業の励行、脱臭施設の整備以外に有効な対策が無いのが現状ですが、労力やコストの面から十分な対策を行うことが出来ないケースが多いようです。 このような情勢を背景として、特別な施設や労力をあまり必要としない「脱臭資材」と呼ばれる商品が多数流通しています。 しかし、脱臭資材を使用している経営者の脱臭資材に対する評価は一定ではなく、その効果についてもはっきりしていません。 確かに臭気の低減効果が認められる資材もありますが、その低減幅は畜舎環境(温度、湿度、換気、清掃状況等)の変化に伴う臭気の変動幅を超えるほどの効果ではなく、脱臭資材のみで臭気対策を完結出来るものではありません。 |
||
 |
 |