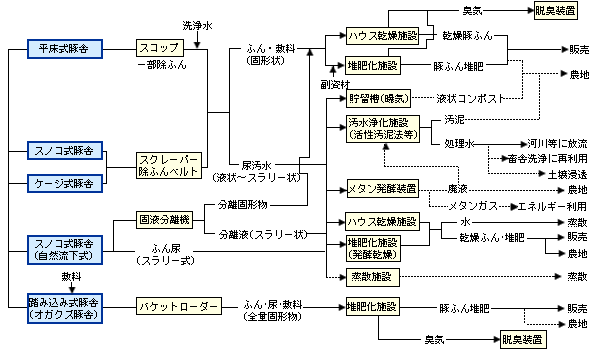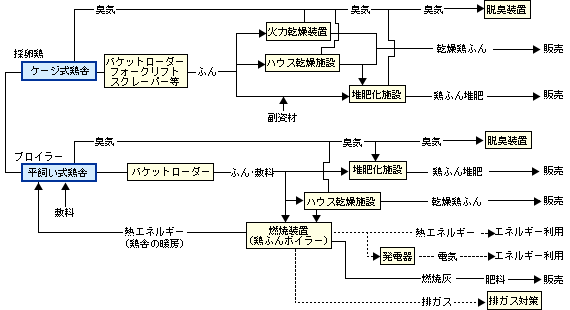| (3)家畜ふん尿処理技術の基本 それでは、家畜ふん尿を肥料資源として有効利用し、環境への負荷を軽減するにはどのようにすれば良いのでしょうか。家畜ふん尿の処理方法には様々なものがあり、どの方法を選択すれば良いのかを決めるのは大変難しく、せっかく大きな投資をしても期待した結果がなかなか得られないケースも少なくありません。 どのようなふん尿処理方式を選定すべきかは、1)農地面積と飼養頭羽数、2)立地条件、3)社会的条件、4)気象条件、5)労力的条件、6)経営的条件などを十分検討し、これらの条件に合った処理・利用方法を選定する必要があります。 たとえば、近隣が畑作地帯ならば堆肥は近隣の農家で利用されますが、畑作地帯が無いならば、堆肥製品の袋詰めなどをして広域流通を考慮した処理方法が必要となります。汚水の処理については、水質汚濁防止法など地域の環境規制をクリアー出来る処理方法を選択する必要があるし、処理水を放流する河川などが周辺にない場合には、農地施用を前提とした処理方法を選択する必要があります。また、すぐ近くに民家があるような場合には、悪臭や衛生害虫の防除に重点を置く必要があります。
|
||||||||
| (4)固形物処理か、スラリー処理か、汚水処理か ふん尿処理・利用の体系としては、固形物処理、スラリー処理、汚水処理の3つの選択肢があります。鶏と肉用牛は固形物処理が主流ですが、乳用牛と豚はいろいろな選択が可能になっています。 スラリー処理は家畜の管理および施設面が簡便であるため、ヨーロッパなどではスラリー処理(貯留、強制発酵、メタン発酵)が主流となっており、スラリーは自分の農耕地へ還元しています。しかし、県内の畜産農家でスラリー全量を還元するのに十分な土地面積を所有する農家はほとんどないのが現状であるため、安易にスラリー処理を選択するべきではありません。 したがって、ふん等の固形物と尿等の液分を畜舎内で分離する構造を導入するか、固液分離器の導入による固形物処理(堆肥化、乾燥、焼却)と汚水処理(貯留、浄化処理、簡易曝気、蒸発濃縮、土壌処理)を組み合わせた方法が考えられます。ただ、この方法は固形物処理と汚水処理の2系統の処理施設が必要なためコストおよび労力が多く必要となります。 |
||
 |
 |