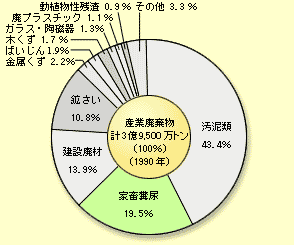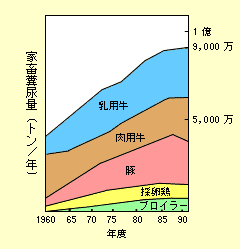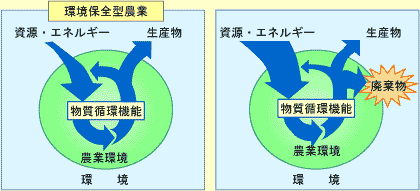| (1)大量に発生する家畜ふん尿 日本で1年間に発生する廃棄物はどのくらいかご存じでしょうか。国民生活に伴なう家庭ゴミなどの一般廃棄物が約5,000万トン、産業廃棄物が約3億9,500万トン、総計約4億4,500万トンにもなります。そのうち家畜ふん尿は約9,000万トンにのぼると試算されており、水質汚濁、悪臭問題等の公害問題を引き起こす原因にもなっています。 この大量に発生する家畜ふん尿の責任はいったい誰が負うのでしようか。それは畜産業(農家)が負わなくてはなりません。この制度を汚染者負担原則といい、公害を起こさないよう、自ら費用を負担して必要な対策を行うべきであるという考え方で、現在では、世界各国で環境保護の基本となっています。 それでは、毎日、発生する家畜ふん尿をどのように処理していけば良いのでしようか。
|
||||||
| (2)環境保全型(資源循環型)畜産のすすめ 今日の農業は生産性の向上を主眼とするあまり、農業環境における物質循環機能が破綻し、リサイクルがきかない廃棄物が多量に発生し、環境問題を引き起こしています。そこで、今、求められているのは、本来の物質循環機能を生かし、生産性の向上を図りつつ、環境への負荷の軽減に配慮した持続的農業が環境保全型農業です。 それでは、畜産にとっての環境保全型農業とはどういうことでしょうか。それは、これまで廃棄物として廃棄していた家畜ふん尿を有機物資源として作物生産に積極的にリサイクルすることです。 日本の畜産は安全で、おいしく、栄養価の高い食品を生産する社会的貢献度の高い産業です。 しかし、その一方では危険・汚い・きつい・臭いの3Kならぬ4Kの汚名を着せられ、環境に優しくないイメージがあります。 有機農業や環境保全型農業への関心が高まっている今日、有機質資源として家畜ふん尿の利用促進を図り、畜産が環境保全型農業の中心としての役割を果たしてはどうでしようか。
|
||||
 |